9月、お変わりなくお過ごしでしょうか。
まだ残暑の厳しさがありますが、少しづつ秋風を感じるようになりました。
季節の節目。
これから年末に向けて、また一段とお忙しい日々かと存じます。
ほんのひとときでも、四季の香りを感じて自分に還る。
豊かな心の時間を愉しんでみてはいかがでしょうか?
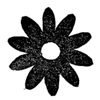 今月の香りは、『菊』
今月の香りは、『菊』

長月と呼ばれる9月は秋のはじまりを告げる月。
重陽の節句でもある9月は、菊のお花がテーマです。
中国の陰陽思想では、奇数を『陽』とし、縁起の良い数とされていました。
その中でも最大である9が重なる9月9日を、最もめでたい「重陽」と呼んだのが始まりです。
菊のお花を生けたり、お酒に花びらをうかべたり。
縁起良きこの季節ならではの安らぎを感じるのもよいものです。
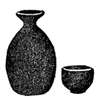 「秋菊有佳色(しゅうきくかしょくあり)」
「秋菊有佳色(しゅうきくかしょくあり)」
「秋菊有佳色(しゅうきくかしょくあり)」という禅語はご存知でしょうか。
「秋の菊が美しい色をしている」という意味の言葉です。
魏晋の詩人・陶淵明-とうえんめい(陶潜-とうせん)の「飲酒二十首」その五の一節。菊を詠じて隠逸の心境を表した有名な詩です。
日本では、お茶室やおもてなしのお席の掛け軸の言葉として、よく使用されます。

この詩の背景
この詩は1500年以上前の中国の田園詩。
魏・晋・南北朝は戦乱と政権交代が続いた混乱期にあり、陶潜は士大夫(知識階級)は清廉を保つか、権力に迎合するかで悩んだ時代。
陶潜は政治腐敗を嫌い官職を捨て、自然に帰る道を選びました。自然と酒を友として過ごす中で、自然を詠う『隠逸の文学』を確立しました。
菊が中国において「隠者の花」と呼ばれるのは、詩人・陶潜が世俗を離れ「菊」を愛で、隠棲生活をしていたことが関係しています。菊は秋霜にも耐えて咲く花で、俗世に染まらない高潔さ・孤高を象徴しました。

この詩からの学び
一觴雖獨進(一觴獨り進むと雖ども)
この一節から読み取れるのは、孤独や寂しさではなく、詩人・陶潜は、自己と向き合い森羅万象と対話する時間を選びました。
現代を生きる私たちは、常に、SNSが身近にあります。
たとえ、一人で過ごしていたとしても、本当の意味での一人の時間を過ごすこと。これは、意識的に選択し、自己に与えなければ得られない貴重なものとなっています。
『足るを知る』『只今ここに生きる』
詩に登場する一杯の酒、菊の花、夕暮れの静けさ、鳥の声など。
こうした 『ささやかな日常の一場面にこそ、生の喜びがある』と詩人は伝えています。
この詩からは、禅における『足るを知る』『只今ここに生きる』に通じます。
いま、私たちが現代を生きる上での『生き方』が問われているかのような詩です。
陶淵明「飲酒二十首 其七」
⚫︎全文はこちら
秋菊有佳色 秋菊 佳色あり
衷露採其英 露を衷みて其の英を採り
汎此忘憂物 此の忘憂の物に汎べて
遠我遺世情 我が世を遺るるの情を遠くす
一觴雖獨進 一觴獨り進むと雖ども
杯盡壺自傾 杯盡きて壺自ら傾く
日入群動息 日入りて群動息み
歸鳥趨林鳴 歸鳥林に趨きて鳴く
嘯傲東軒下 嘯傲す東軒の下
聊復得此生 聊か復た此の生を得たり
⚫︎大意(現代語訳)
秋の菊は美しい色を見せている。
露を浴びて咲く花を摘み取り、憂いを忘れさせてくれる酒に浮かべる。
そうして世俗を離れたいという気持ちを遠ざけるのだ。
一杯の酒を、たとえ一人で飲もうとも、杯が尽きれば壺から自然に酒を注ぐ。
日が沈めば、人々の営みは静まり、鳥たちは林へ帰ってさえずる。
私は東の庇の下で口笛を吹き、傲然とくつろぐ。
そのときこそ、しみじみと「生きている喜び」を味わうことができる。
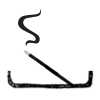 ひと月、ひと香(ひとつき、ひとこう)
ひと月、ひと香(ひとつき、ひとこう)
毎月ひとつ。
季節の香りをお手に取り、今を感じる。
先月の自分
今月の自分
いま、何を思うのか。
やることが多いと、どうしても外に意識が向きやすいものです。
月に一回でも、この香りを手に取った時は、
あなたがご自身に集中できることを願って。
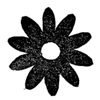 菊の印香-香りと愉しみ方
菊の印香-香りと愉しみ方

こちらの印香は、気品高い優雅な花の香り。
印香は、約1ヶ月ほどほんのり香りが続くので、お皿の上に飾っても素敵です。
毎月のご自身と向き合う時間として。
香台にのせ、火を灯し、
立ち昇る煙とともに雑念を浄化。
新たな気持ちで、また今日を生きる。
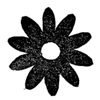 ひと息ついて、香りに身をゆだねる『今ここ』の時間
ひと息ついて、香りに身をゆだねる『今ここ』の時間
毎月ひとつの香りと向き合う時間は、
ほんの5分、10分かもしれません。
しかし、ほんの短い時間であっても、
ご自身と静かに向き合う貴重な「ひととき」というものは、
人生においてかけがえのない時間ではないでしょうか?



